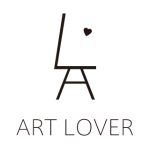Contents
ギュスターヴ・モローのここがすごい!
白百合を掲げる一連の絵
ギュスターヴ・モローは精巧なタッチと艶かしい肌が特徴的な画家だが、その美麗な絵はどこか「不吉さ」を我々に感じさせるものが多い。
彼の代表作は一連のサロメ連作であるが、その中の一つ「ヘロデ王の前で踊るサロメ」は白百合を掲げたサロメが虚空に手を伸ばし、今まさに踊らんとする構図を描いた絵である。
この絵に限らず、モローの絵には「白百合を掲げた人物の絵」が見られる。
例えば、これとよく似た構図の真紅に塗りつぶされた「サロメ」もその一つだ。

この絵はモローが「象徴主義」であるといわれるゆえんをよく表している。
豪奢な衣装(7枚のヴェール)をまとったサロメ、手をのばし、例によって純白の百合を掲げ緊張感、ただごとでない空気、その姿は悪女というより、託宣を得るシビラのようだ。
血のように赤い背景はこれから始まる悪辣きわまる冒涜の宴を予感させるようである。
それでもモローのサロメは神々しい。
己のなすこと全てを承知して、それでもなお超然とそれを見据えているように見える。
この悪徳の花はキリスト教的な神とはまた別の神なのだ。
彼女は神として恐れることなく神に対峙する。
モローのサロメ題材として最もよく知られている「出現」は素描の段階では首の出現におびえるサロメが描かれていたらしい。
それを今日我々が目にする堂々と睨みつけるサロメにモローが変えたのは、この2対が同等であると表したかったのだろう。
モローが白百合を掲げる人物として描いているのはギリシャ神話のヘレネーが挙げられる。
ギリシャ神話における「最も美しい人間の女」とされ、その美しさによって人類で初めての戦争(トロイア戦争)を引き起こした人物とされる。
「トロイヤの城壁の下のヘレネ」は一輪の花を手に持ち、いかにも楚々として立っている。
その清らかそうな姿は悪徳の花サロメとは正反対に見えるが、この女はそれにもいよいよ増した不吉さで我々を圧倒するのだ。
スカイア門の前のヘレネ
生臭い血の匂いが漂ってきそうな中を純白の百合を掲げ進むサロメの美貌は、もはやのっぺらぼうとなっている。
荒々しい絵の中で男を惑わせる清楚然としたうわべは消え、ヘレネの本性があばかれる。
そして、栄光のヘレネ
薄暗い闇の中、軍人を従え嫣然と笑む女神からはモローの女性観が見えてくるようである。
文:一染
セメレー、神と対峙すること

恐ろしいほど緻密な絵だ。
モローのセメレーはその圧倒的迫力と荘厳さにおいて、代表作のひとつとも言われている。
単に放射線状に聖者や御使いが描かれるのでなく、左右のうら若き女、慈悲深き乙女マリア(しかしその顔は髑髏のように目がポッカリと抜け落ちている)
生命の悦びとなるはずの色とりどりの鮮やかな草花すら、ここでは心なき神の威厳を演出するためのいわば寺院のレリーフと同じ存在となっており中央の大神ゼウスは同作者の「サロメ」と同様、その肉体に草花のごとき刺青を刻んでいる。
サロメの刺青は「霊的磁場」であると評した人がいた。
当然ただの刺青であろうはずもない。神と成るときにその肉に現れる草花の模様は千弁の蓮華であり、マントラである。
そしてかつてサロメが持ち、ヘレネーが持った乙女マリアにあっては「純潔」、モローにあっては「血を流す神」(最も表面的には)の象徴たる純白の百合を、今度は男神たるゼウスが掲げるのだ。
流されるのはセメレーの血である。彼女はゼウスの膝の上で畏怖と驚愕をその身にあらわしている。しかしその姿はまるで人間的な動作ではない。彼女もまた他の神々と同様に、神のごとき乙女なのだ。
目をかっと見開きおおよそ慈悲など乞えそうもないゼウスの顔は、あるいは当時盗掘者に仇なすと言われていたスフィンクスをモデルにしたのかもしれない。
神話では「怒ったゼウスが雷光に包まれた真の姿を現したので、セメレーは雷光に当たって焼け死んで」しまったとあるが、ここでセメレーは雷光にあたってもいないし焼け死んでもいない。
モローは幻視家の直感として知っていたのだ。「セメレーが死んだのは雷光のためではない」
セメレーは神の姿を直接見たことで死んだのだ。
「神の姿を見た」人間で、新約聖書にヨブの話がある。
彼は神を敬い正しい人であり、多くの富を得ていたが、サタンの「ヨブは多くの恵みを神から頂いているのだから、神を敬うのだろう」という言葉に「それではその恵みを失ってもヨブは神を敬うだろうか」と、神の手によって恩恵の数々を奪われてしまう。
「ご利益がなければ人は神を信仰しないのか」がヨブ記の主要テーマである。
ヨブは富を失い家族を失いまた健康を失い、病を得て一人蔵の中で全身に襲う猛烈な痒みと激痛の中、陶器の破片で体を掻き神に祈っていた。
ヨブの妻はなおも信仰を失わない夫を見て哀れみと嘆きの中で
「あなたはあなたをこんなにもした神へまだ敬虔でいるのですか。神を呪って死になさい」と言うと、ヨブは「我々は神から幸福を賜った。同じように不幸も頂こうではないか」と答える。しかし苦しみが続くにつれ、ヨブの信仰は徐々に揺らいでいく。
「なぜ、わたしは母の胎にいるうちに死んでしまわなかったのか。せめて、生まれてすぐに息絶えなかったのか。なぜ、膝があってわたしを抱き、乳房があって乳を飲ませたのか。それさえなければ、今は黙して伏し、憩いを得て眠りについていたであろうに。」
それを見た三人のヨブの友人がヨブをたしなめる。
それぞれ主張は違えど、三人とも因果応報論に基づいた主張だ。
あなたに何か罪があったのだから、それを反省して神に許してもらえ、と。
だがヨブには心当たりがない。いくらなんでもここまでひどい目に遭うほど神意にそむいた覚えはない。
方々の問答の末、ついに神がその場にあらわれて言う。
「神より小さき者、お前は神の何を知っているのか。私には偉大な計画があるのだ」
難解なヨブ記の最重要シーンの台詞を要約してはいけないだろうが、まあだいたいこんなことを言う。少なくとも私はそのように受け取った。
ヨブにはわからなかっただろうが、後世私たちから見ると「神の偉大な計画」というものはなんとなく理解できる。つまりヨブ記の主要テーマである「ご利益がなければ人は神を信仰しないのか」 である。
さてその答えをヨブは意外なかたちで出した。
ヨブは姿をあらわした神に跪き、許しを請い信仰を誓ったのだ。
それはむしろ神の語った言葉というよりも「神の姿を見た」ことによる感化である。
つまりセメレーがゼウスの姿を見たことによって死んだようにヨブも神の姿を見、全身に雷光が走ったように感化されたのだ。
ヨブはそこで「神が偉大であること」を悟ったに違いない。しかし文章を読むだけの私たちには理解できない。そこがヨブ記が難解だと言われる理由だと思う。
神は敬虔なものにも信仰なき者にも姿を現したが、悟ったのはヨブ一人であった。
さて、セメレーはどうであったか。 セメレーはゼウスの威厳を受けて死んだ。
そして彼女は後に太陽の光を受けて輝く、月の女神と同一視されるにいたる。
文:一染
思わず引き込まれる妖艶で優美な架空の世界
ギュスターヴ・モローの絵で有名のものとしては、サロメやトロイのヘレネなどがあります。伝説や神話などの世界のできごとが、幻想的で強烈な魅力をもって見るものに迫ってきます。
モローは、1826年、建築家の父と音楽家の母の間に生まれ、8歳のころからデッサンを書き始めたそうです。
その作風は、写実主義や印象派などの19世紀後半のレアリスムの流れとは孤立し、幻想的、奇怪・異様な雰囲気があり、寓意的、装飾的なものです。
モローは、若いころは、シェークスピアを題材にドラクロワ風の絵を描いたり、のちにはイタリアでミケランジェロやラファエロなどの模写もしたそうです。モローの絵の中には、いろいろな要素が入って独特の世界を作っています。インド風の建物、アラビア風の衣装、レンブラント風の光、アラベスクのような精緻な装飾など、独特な美しい世界が迫ってきます。
モローは、晩年、世間との接触を避けるようになって孤独な中で自分のテーマを追求しました。それは、自分には見えないもの、自分が感じるもの、内部の感情の永遠性だけを表現することだったそうです。モローの作品には、制作年代がわからないものも多いそうですが、それは、モローの絵の世界が現実の時間を超越していたからだろうともいわれています。
文:レモングラス
ロマッチックなサロメ図鑑
ギュスターヴ・モローと言う画家は、西洋美術史をやると、だいたい弾かれます。歴史やその時の流行にことごとく当てはまらない、こだわりの画家。レアリズムから新古典派、そしておなじみ印象派がやってきた頃、ほぼその波に乗りませんでした。あえていうなら、風景画が流行るぞと言う時に、ギリシア古典や聖書を題材に描くという、時代に流行に逆行するような作品を多く描いていました。主に小品が多いですがその一つ一つは宝石のよう。微細に大切に描いたであろうことが見ると分かります。
モローの一連の作品群の中でも特に印象に残るのが、サロメを主題にしたもの。聖書の主題のひとつや、ファムファタルの象徴として主題になりますが、その多くは銀皿に洗礼者ヨハネの首を乗せた構図で描かれます。一見すると少々グロテスクなものもあります。けれども、モローのサロメはまるで乙女のよう。洗礼者ヨハネの首も銀皿にポンとは乗せていません、「出現」と題されたサロメは指さした先に首を浮かせています。オスカー・ワイルドの戯曲にある、踊りのご褒美に何が欲しいかと問われ「ヨハネの首を」と言うシーンが思い出されます。そしてだいたいがサロメと洗礼者ヨハネの首を書くことで完成してしまうこの主題を、繰り返し何パターンも描いています。サロメの衣装はそのたびに変わり、服の模様を肌にそのまま描いた刺青のサロメと称されるものもあります。そんなモローのサロメの中でも変わり種が上野の西洋美術館常設展示にあります。そのサロメは有名な踊りのシーンではなく、囚われの洗礼者ヨハネのもとを訪れるサロメです。牢の中を覗けずにいるのがモローの描くサロメのロマンチックな所。自分で所望しておきながら首を落とされる所を直視できない、そんな繊細な乙女のサロメです。ファムファタルや悪女の象徴として描かれていたサロメに、繊細な乙女の要素を盛り込んだ画家は他に思いつきません。サロメだけで一冊画集が作れそうなほど描いてきたモローだからこそ成せた技だと思います。
文:クロエ
美しくもショッキングなモローの絵画
ギュスターヴ・モローは象徴主義の先駆者として1800年代にフランスで活躍した画家です。神話や聖書を題材とした絵画を多く手がけ、神秘的で物語性を含んだ画面は観るものを独特の世界観に引き込みます。
彼の代表作である「旅人オイディプス」やその制作過程で描かれた水彩画などは同年代の他の神話画とは異なる、どこか強烈でグロテスクささえ感じさせるような生々しさを孕んでいます。

画面中央で翼を広げるのは美しい女性の顔に獅子の体をもつ怪物スフィンクス。そしてその足元に折り重なるのはスフィンクスの謎かけに敗北した犠牲者たちの無残な姿。モローはスフィンクスをただ美しく若い女性の姿で表現しただけではなく、その足元に幾重にも重なる犠牲者たちを配置することで怪物の残虐性と共に、その場面の張りつめた空気感さえ描き出しています。目を見開き旅人オイディプスを見据えるスフィンクスの横顔は、絵画を観ているこちらまでも見張っているかのような鋭さと迫力があり、対して杖に寄りかかるオイディプスは弱々しく項垂れ小さく身を縮めているようにも見えます。
モローはこうした神話を題材とする一方で、聖書を題材とした絵画も残しています。ヘロディアの娘、サロメを描いたものが有名でしょう。

中でも印象的と思われる作品が「出現」だと思います。踊りの褒美に洗礼者ヨハネの首を求めたというサロメを題材とした作品は様々な画家たちによって描かれていますが、モローの「出現」に描かれている場面はそれらの作品とは全く違う、強烈なワンシーンとなっています。
装飾的な衣装に身を包み踊るサロメが左手で指し示す先には宙に浮いたヨハネの首が描かれ、鮮血を滴らせながらジッと彼女を見つめているのです。
日本の怪談に登場する生首を彷彿させる、どこか不気味な絵画のようですが、ヨハネの首を見つめる踊り子サロメの姿は毅然として美しく怯えた様子はありません。
モローの作品は、繊細な筆使いで描かれつつもその美しさの中にショッキングな描写を入れることで独特の空気感を創り出し、物語の重厚な世界を閉じ込めているように私は思います。
文:甘蛙
ギュスターブ・モローの作品紹介
「出現」 – ファムファタルとしてのサロメを初めて描いた画家
ギュスターヴ・モローは19世紀末のパリに生まれ、パリで活躍した画家でした。
その技法は繊細にして優美。そして神秘的で幻想的。
美しいけれど、例えばルノアールのような幸せを感じさせる美しさとは違います。どこか身のすくむような耽美な美しさであふれた画面を描き出した画家でした。
このモローの功績の一つに、聖書に出てくる少女「サロメ」を、意思を持ったファムファタルとして描いたことが上げられます。
「出現」という題された作品がその作品です。
その前に、少しサロメについて説明しておきましょう。
サロメは聖書に出てくる人物で、ユダヤの王女。
父の弟…実の叔父に父を殺され、その叔父が父の代わりに王座に就きます。
それだけでなく、叔父は実の母と結婚までしてしまうのです。
父を殺した人物が義理の父となる。なかなか複雑な家庭環境ですよね。
この叔父は、キリストに洗礼を授けたヨハネを異教徒として逮捕。監禁しています。
そしてある時サロメは、舞いを舞った褒美に「ヨハネの首を切り落としてくれ」と王である叔父にねだるのです。
聖書ではここは実にあっさりと描かれています。
「サロメは舞の褒美にヨハネの首を欲しがり、ヨハネは殺された。」だいたい、この程度の記述です。
そしてこの程度の記述が、多くの芸術家たちを刺激しました。
モロー以前は、サロメはヨハネを嫌悪する母にそそのかされただけだろうと解釈されてきました。
しかしモローはこの「出現」で、初めてサロメを「自分の意志でヨハネの首を欲しがるファムファタル」(男性の運命を狂わせる美女)として描きました。
そして、この絵がきっかけで有名なワイルダーの戯曲「サロメ」が描かれ、今の狂気の悪女というサロメのイメージが出来上がったのです。
しかしそういった文学的な背景だけでなく、絵の美しさも素晴らしいものがあります。
構図が、ほぼ真ん中に空中に浮かんだヨハネの首。そしてそれを指さすサロメというショッキングなもののために、技術的な面に目がいかないかもしれません。でも例えばサロメの衣装。半裸にきらびやかなアクセサリーを付けているのですが、その宝飾の描かれ方の細かさ、美しさ。サロメのベール、背景のアーチ、画面左の柱に使われている青…というよりはラピス色の美しさ。色彩の配置の巧みさ。背景まで細かく書き込まれた緻密な模様。絵画作品としての魅力は語りつくせないものがあるといえるでしょう。
画面中央に血の滴る生首があるというショッキングな構図に目を奪われずに、絵画作品としてじっくりとその超絶技法を味わって欲しい作品でもあります。
文:小椋 恵
ギュスターヴの「オルフェウス」の切ない作風が大好きです。
私は、ギュスターヴ・モローの「オルフェウス」が大好きです。初めて大塚国際美術館でこの作品を見た時、切ない顔の女性と、どことなく暗く、でも幻想的な雰囲気がとても印象的な作品だと感じました。

ギュスターヴ・モローは、パリで生まれてパリで活躍し、パリで亡くなった最初から最後までパリに縁のある芸術家として有名です。象徴主義の代表的な作家で、聖書や神話を元にした神秘的な作品を数多く描きました。途中でイタリアのローマへ留学し、そこで数多くの芸術家と出会います。晩年はアトリエで黙々と作品を描いていたと言われており、パリにあるギュスターヴ・モロー美術館で彼の作品を数多く見る事ができます。オイディプスとスフィンクス等の作品が有名です。
「オルフェウス」は、古代ローマのトラキアと言われる場所で伝説的な詩人と言われたオルフェウスの首と、その首を切なそうに、思い深そうに抱えているトラキアの巫女が描かれています。
晩年のオルフェウスは、女性を避けていたそうですが、トラキアの女性たちはそれに狂乱してオルフェウスを儀式の時に八つ裂きにして頭と首を川に流しました。その頭と首を拾った優しくも切ない顔のトラキアの巫女が何を考えていたのかがとても気になる、とてもロマンのある作品だと思います。
文:るるるるん
関連記事
あわせて読みたい!
『ART LOVER』現役の作家紹介ページに載りませんか?
当サイトはこれまで過去の有名な作家や作品を中心に取り上げてきましたが、微力ながら支援したいという思いも兼ねて、現役の作家さんたちも厳選しつつサイト内で紹介させていただこうと思っています。 インタビュー形式のアンケートよりご応募いただけます。詳しくは下記応募ページをご覧ください! http://art-lover.me/new-artists-wanted/ 周囲に作家活動に真剣に取り組んでいる方がいらっしゃれば、上記募集ページをSNSでシェアしたり、URLをお伝えいただけたりすると幸甚です!